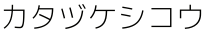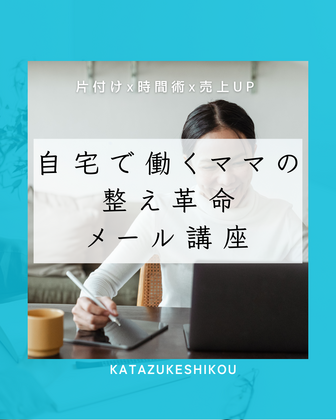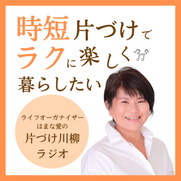郵便をスムーズに出すための工夫
切手の手作り整理収納グッズ

昨年の郵便料金の改定から、郵便料金がイマイチ覚えられなくなりました。
そんなときに限って、郵便を出す機会が増えて、毎回郵便料金をネットでググるか、郵便局に行って重さと料金を確認してもらっていました。
20年近く前の秘書時代、定形郵便料金はもちろん、定形外料金も記憶していたし、手で持てば、大体の重量もわかって、25gまたは50g以上か、大体当てていました。
(発送前には、重量はちゃんと量って切手を貼っていましたよ。)
でも、今となっては、そんなカンも鈍り、定型郵便もハガキの料金もアヤフヤに。
これでは毎回手間だし、非効率的だ…と反省して、すぐに切手を貼って発送できる仕組みを作り直しました。
私の最新切手収納 家にあるものでササッと手作り
切手は、よく使う額面を小袋で分け、クリアファイルに入れて、手帳に挟んで持ち歩くようにしました。おかげで、出先でもササッと郵便を発送することができます。

私がよく使う切手は、 定形郵便の25g84円、50gまで94円、
定形外120円、140円
ハガキ63円 などです。
郵便局で切手を購入したときのビニール小袋を、適当な大きさに切って、出し入れしやすくしています。

定形封筒を半分に切り、下半分と上半分それぞれ小袋として使っています。

上半分は、切った底の部分はマステを貼り付けて閉じました。
下半分は、口が開きやすいよう、後ろの面だけ上から1センチほど切り取って、封筒の口のようにしました。
古い券種は、不足金額の額面の切手もセットで入れています。
- 82円切手と2円切手のセット (さらに10円切手もセットにして、94円でも出せるようにセット)
- 62円切手と1円切手のセット など

これらをA5サイズのクリアファイルにまとめて入れています。
クリアファイルの表紙には、郵便料金表を印刷して表紙に付けています。印刷した紙を直接貼り付けるのではなく、別の無色透明のクリアファイルをちょうどよい大きさに切り、マステで貼り付け、その中に料金表を入れました。こうすることで、料金表の紙がいたみにくく、もしまた改定があった時に、紙を差し替えやすいかなと思って、こんな風にしました。

切手セットを作ったので、便せんセットも入れてしまおうかと考えましたが…。実際、手紙はそんなに頻繁に書かないし、持ち歩く必要はないな、と思いとどまりました。(自宅での収納は決まった場所にあります。)
けれども、ハガキはたまに書くので、思い立ったときにすぐ書けるよう、官製葉書3枚と、絵葉書3枚も入れました。

手元にある材料で、簡単に。エコにもなります。
切手の整理をしようと思いたったときに、百均などで名刺サイズのクリアケースなどを購入することも考えました。ただ、あまり人に見せるものでもないし、家に余っているもので簡単に作っちゃいました。
最近は、いろんな文具や収納グッズが豊富で、百均などでもすぐに買えるので忘れがちですが、以前は、古封筒を書類整理などによく使っていたのを思い出しました。 人によっては、もっと見栄えにこだわることもアリと思いますが、自分で使うには十分、満足しています。
収納グッズが豊富な時代なので、片づけようと思うと、つい収納グッズを増やすことを最初に考えがち。でも、まずは手元にあるモノで何とかしようと考えるのって、案外大切だと思いませんか?そうすれば、モノを不用意に増やさずにすみますし、買いに行くより早いかもしれませんよ。
手元のアイテムでは不便で、どうしても新しいモノがあるほうが便利だな、効率的だと思ったら、それから購入することにしても遅すぎることはありませんしね。
何かの参考になればうれしいです。
本日も最後までお読みくださって、ありがとうございました。
関連エントリー
-
 モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?
「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ
モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?
「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ
-
 実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話
年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今
実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話
年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今
-
 「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法
PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分
「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法
PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分
-
 人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー
| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!
12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講
人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー
| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!
12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講
-
 段ボールが散らからない!
捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場
ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく
段ボールが散らからない!
捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場
ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく