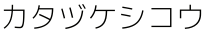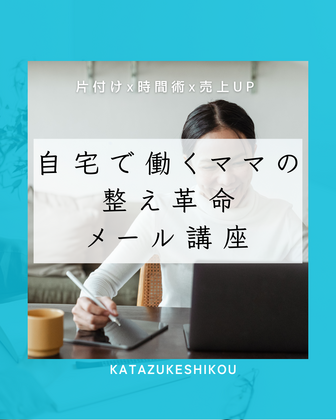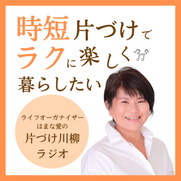書類の捨てどき、決めていますか?
書類保存期間ルール
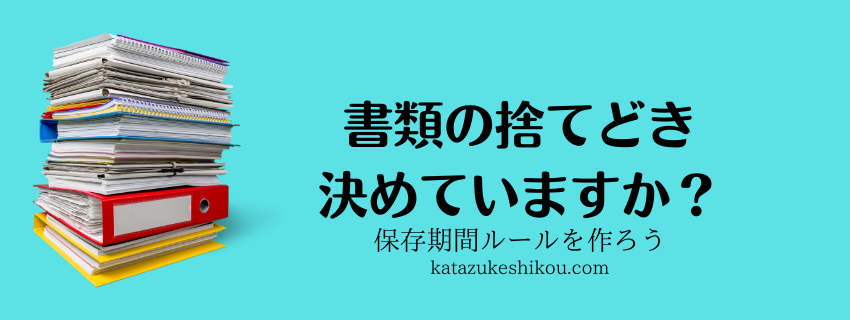
ため込みがちな書類の山。
いま使っている書類は
手元に置く方が良いと分かっても
それ以外の書類を
どのように分けて保管すべきか
いつ廃棄すべきか、
お悩みの方も多いと思います。
書類は、分類していくと、
すぐに廃棄できるモノもあれば、
使わなくても保存が必要な書類あります。
「一応取っておこう」と残すばかりでなく
「いつまで保管するか」を最初に決めておくのが
溜め込む一方になるのを防ぐ一番簡単な方法です。
今日は、書類の旬と保存期間についてご紹介します。
書類の一生
まずは、書類の流れについて簡単に。
どの書類も、作成後は、活用→保管→保存→破棄の5段階をたどります。
活用:進行中の案件。リアルタイムで使う→デスク上のトレイ、デスクの引き出し、共用キャビネットなど、取り出しやすい位置に収納。
保管:進行中の案件ではないが、終わったばかりなど。→手元のキャビネットや、事務所内のすぐ取り出せる場所に、収納しておく
保存:日常的には使わないが、法定保存期間の定めにより、文書箱などに入れて収納しておく。事務所にスペースがない場合は、書庫やレンタル倉庫などの保管もあり。
破棄:保存期間が終了したら、内容に応じて、シュレッダーや溶解処理をして処分。
ご参考までに、
法律で保存期間が定められているものは、
目安として、総務関係は2〜5年、
経理関関係7年、会社法関係は10年です。法的なルールがない書類の保存期間
ここで疑問になるのが、法的ルールがない書類の保存期間。
例えば、カタログ類など、資料関係。
自分のメモやノート。
基本的に、情報は生物なので、
古い情報はどんどん破棄していくのが正解。
ただ、どのタイミングで古いと判断するかは、
業種や、職種によっても少し違ってくると思います。
古くても大切な記録があれば、それはそれで残すのはOKです。
例えば、流れの早い業界なら、数ヶ月でもう古いと判断されたり、
モノによっては、2−3年は必要と考えられたり。
ただの参考資料であれば、
スキャンして電子化しやすいモノも多いので
紙の資料は減らしやすいですし、
また、ウェブで取れる資料は、
手元に残す必要はないかもしれません。
ここは、
自分で決めるか、社内で相談して、
自社ルールを作り、エクセルなどにリスト化すると良いです。
リスト化したら、ファイルごとに保存期間を明記し、
年末の大掃除のタイミングなどで年に1回見直し、
破棄するサイクルを作ります。
書類の旬は、自分で決めてルールを見える化して、社内共有できるようにしましょう。
そうすると、書類がたまる一方の状態は避けられます!
どなたかのご参考になれば幸いです。
<参考>
<参考記事>
書類が多すぎて、どこから手をつけて良いかわからない!?書類整理の洗い出しアイデア
会社の書類の整理整頓書類整理の仕組み化 ②会社全体の書類を把握するには?
会社の書類の整理整頓 簡単に素早くできる方法は?書類整理の仕組み化①下準備編
会社の書類の整理整頓書類整理の仕組み化 ②会社全体の書類を把握するには?
会社の書類の整理整頓 簡単に素早くできる方法は?書類整理の仕組み化①下準備編
関連エントリー
-
 モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?
「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ
モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?
「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ
-
 実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話
年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今
実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話
年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今
-
 「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法
PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分
「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法
PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分
-
 人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー
| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!
12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講
人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー
| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!
12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講
-
 段ボールが散らからない!
捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場
ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく
段ボールが散らからない!
捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場
ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく